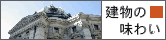設計:辰野金吾
| * | 日本人建築家による実質上はじめての本格的な様式石造建築であると共に、日本人の手による最初の国家的建築 |
| * | 1Fは堅牢で銀行を守り、2Fはルイ16世様式を参考にした主知的かつ厳格なもの |
| よく知られているように、 日本銀行本店は、辰野金吾が日本人建築家として実質上初めて本格的な様式石造建築を設計したものである。 それは同時に日本人の手による最初の(大がかりな)国家的建築でもあった。 それを日本人が自らの手で建設したのである。 設計は1888年に着手された。辰野は1879年に工部大学校(今の東大)を卒業し、 83年までロンドンに留学していた。 85年には煉瓦造による様式建築である銀行集会所を竣工させている。 その作風は恩師J・コンドルの作風に似ながらも、 彼自身がロンドンで見たジョージアン様式などを引き継ぐものであった。 かなり後になり設計事務所を構えてから、 ロンドン留学時代から温めていたクイーン・アン様式の「もじり」を始め、これが世に言う辰野式である。 |
 |  | |
  | ||
 |  |
| さて、日本銀行であるが、真ん中が凹んだコの字型をしていて、左右両ウィングが張り出してきている。 その中央はというと、防御を重んじて手前に壁が巡らせてある。 だから奥まったファサード(であった筈のもの)は見えないし、 そこにあるであろう庭も入口も全く見えない。 1F部分は石積みの荒い感じを出して2Fと差を付けてある。 |
| ピアノノビレ(主階)すなわち2Fは、1Fの壁よりずっと優美である。 これは辰野がベルギー銀行のルイ16世様式を参考にしたと言われている。 ルイ16世の時代(18世紀後半)とは新古典主義の開始時期であり、 パンテオンやルイ15世宮殿(現在のホテル・クリヨン)が建てられた。 バロックのような大げさな身振りはつけずに、当時知られていた限りでの古代オーダーに比較的忠実で (後期になると発掘が進んで古代ギリシアに完全に忠実になる)主知的・厳格を旨としていた。 私はベルギー銀行は見たことないが、ホテル・クリヨンなんか割とこの日銀2Fに似ている。 |
| 遠くから見ると、日銀本店は古い様式建築を外国で見ているような雰囲気をしっかり持っている。 しかし近くで見ると、例えば左右ウィング2Fのオーダーの背後が無装飾で間延びしているとか、 ちょっと気になるところがある。ペディメント(一番上の三角破風)の中も無装飾で間延びする。 辰野の様式建築は片山や曽禰と比べてあまり上手だと言って褒められないが、 単に形態の配置の問題として見ない方が良いと私は思う。 日本で作る様式建築には、装飾の問題が非常に大きいように思える。 つまり石造装飾の良い職人が日本に少なかったとか、そういう事情が何かあるという事だ。 装飾というと現代建築ではバカにされるが、様式建築にとっては非常に重要な要素である。 パリの古い建築は大抵は装飾でコテコテである。ホテル・クリヨンだってそうだ。 このコテコテ・ギトギトを学びなさいとは言わない(あんまりいいものだと思わない)。 |
 |  | |
  | ||
 |  |
| むしろ私が辰野のファサードと共通する「間延び感」を感じるのは、 NYのマッキム・ミード・アンド・ホワイトが建てたボザール風建築の一部である (時代的にはMM&Wの方が後だが)。 彼らものっぺらぼうの壁面を平気で見せるのだが、一つ辰野の建物と決定的に違うところがある。 それは、必ずどこかにスゴく良くできた装飾彫刻があって、全体の面を見事にシメているのだ。 つまり何が言いたいか、日銀本店のように多少間延びしてもいいんだけど、 もしそうするならどこかにそれ全体をシメるような、 超よく出来た装飾彫刻を入れないといけないと思うのである。 それがない‥。 |
| もし装飾が入らないなら、せめて余計な線一本でも入れた方がいい気がする。 実際、辰野が建てた部分の右側にある長野宇平治(だと思う)による増築部分を見ると、 さっき言った2Fオーダーの背後に線が回してある。 まぁこの長野の増築が良いかというと、これまた問題だが‥。 ちなみに私が間延びと称したこの日銀本店でさえ、 のちの(辰野の)日銀大阪支店と比べるとゴテゴテしていると言われる。 う〜ん、ゴテゴテというかモッサリしてるんだよねェ。 でもこのモッサリ感も、キレのいい装飾を入れれば見違えると思う。 |
| 結局、装飾の問題は石造装飾の良い職人が日本に居なかったか、 あるいは辰野が装飾の指定を充分にしなかったか、そのどちらかであろう。 でも全般的に言って、片山東熊の作品にしても妻木頼黄のものにしても、 私が知る限り装飾ディテールのレベルはそれほど高くない。 装飾のレベルが高いと思ったのは、僅かに岡田信一郎の 明治生命館 だけである。 いや、これも装飾が多いというのではない。しかし装飾には本当に命が入っていて、 その意味でご当地ヨーロッパの優秀なもの(或いはMM&Wのもの)に比肩されうると思ったのだ。 もしかしたら、装飾の問題は大部分の日本人様式建築家にとって鬼門だったのかもしれない。 それで装飾が充実できない代わりに、それを補う形態的な配置の充実を目指したのかもしれない。 |
|