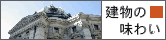設計:丹下健三
| * | シンプルな十字型の構成。8枚のシェルに覆われた純粋的な形態が力強さを感じさせる |
| * | その垂直性が「カトリックの精神」を表し、面の膨らみは「伝統ある勾配屋根の家並みとの調和」を表す |
| 東京カテドラル聖マリア大聖堂は有名だから中学教科書にも載るという。 その最大の特徴は形態(外形)にある。 十字型の平面、8枚のシェルに覆われた純粋的な形態に、精神性と力強さが込められている。 形態自身が持つ表現の力みたいなものは、いかにも丹下らしい感じがする。 しかしそれと同時に、当時のモダニズムでは純粋形態への試みが多く行われていた事を物語る。 モダニズムは全世界で分け隔てなく普及される事を望んだので、(その意味で)コスモポリタンな運動である。 行く前に写真で見た限りでは、そのコスモポリタニズムが表出された作品に思えていた。 |
| 実際に正面から見た時には、私はモダニズムの源泉となったロシア構成主義を感じた。 特に教会の正面左にある鐘の塔に対してだ。 この塔が垂直にピンと立っている姿に、何とも独特のロシア構成主義的な記念碑性を感じた。 それとあと、シェルの表面は写真ではなめらかに見えたが、 実物ではいく筋もの細かい板目が付いていて目立った。 板目とともに全体が金属的な感触であり、これは写真からは伝わってこなかった。 この金属性は直近の現代作品とも通じる何かである。 あと、近くで見るとシェル構造本体の「ふもと」に、 立体構成されたような地下聖堂施設があるのが注意をひいた。 |
 |  | |
  | ||
 |  |
| ぐるっと周囲を回ると、思ったより「でかい」。 この大きさが何より私の感触に先に飛んでくる。 教会も塔も何だかロシアの現代的記念構成物という感じでもある。 教会であるというのは二次的なことにすぎなくて、本質はでっかい記念碑って感じだ。 モダニズムのルーツがロシア構成主義である事をよく表している気がする。 キリスト教の「敬虔」って感じと少し違うと思う。 でも丹下自身の言葉によると、その垂直性が「カトリックの精神」を表しているそうだ。 面の膨らみは「伝統ある勾配屋根の家並みとの調和」だそうだ。 |
| さて、中も見学させてもらった。 カトリックは入場者に寛容だから助かる。 でも結婚式の最中であり、撮影は禁止されていた。 中は、要するにシェルを内側から見ているわけである。 シェルに沿った上へ上へと収斂するような空間であった。 それも記念碑的と見ればみることが出来るけれども、 同時にゴシック教会内部の、上に伸びるような空間と重なる性質を持っている。 その意味では内部の方がキリスト教を感じさせる。 |
 |  | |
  | ||
 |  |
| 内壁は打ち放しコンクリートが時と共に黒ずんで、独特の感触を醸し出している。 何だかNYの TWAターミナル(サーリネン) を連想した。 コンクリの内壁自体が表情を感じさせて、それが独特の世界を醸し出しているからだ。 内部空間のごく下の方に人間がいる。 この小さな集団(に見える)が儀式などを行っている。 伝統的な教会建築だと柱が林立するから、人の集団が全体として固まって見えることはない。 ここは無柱空間だから人の居場所が固まって見えるし、何か淋しくも感じられる。 う〜ん、こんな大きな空間を、柱なしにもろに感じ取りながら礼拝するって、 疲れないかなぁ‥。 |
| まあ、そんなこんなで、東京カテドラル聖マリア大聖堂はいかにもモダニズムらしさを感じさせる、 その意味ではわりと「分かりやすい」建物だった気がする。 |
|