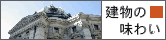設計:アントニン・レーモンド
| * | モダニスト、レーモンドによる飾らない近代建築 |
| * | 静謐、そして集会の雰囲気密度を上げるこじんまりしたインテリア |
| この教会は小規模だが、都心で建て込んでいるので外見に引きがとれない。 全体を遠くから見晴せる視点は少ない。 わりと近くから見上げた時に親しみ深く作られているような気がするが、 建った当初はどういう状態だったのだろう?。 聖堂は側壁が特徴的である。 縦のスリット状開口部がじゃぱらのように並んでいて、外からもよく分かる。 これがこの聖堂の最大の特徴だろう(形態的には)。 この側壁は、群馬音楽センター(1961)になにがしかのヒントというか先行形態になったのかもしれない。 |
| 聖堂の中にはいると薄暗くて、側壁からの光が全体をぼうっと照らしている。 それは光によって聖堂内部が包まれているかの如くであった。 まず目にはいるのが正面の祭壇で、これは写真で有名だから、来るまえからすごいと思っていた。 どこまでがレーモンドのデザインなんだろう?。 とにかくこの形やインパクトを抜きにしてこの聖堂は語れない。 この教会でレーモンドはコンクリートの打ち放しを初めて使ったといわれるが、 内壁のコンクリートはスクラッチしてあって、いわゆる我々が普段みる打ち放しの感じではない。 さて例の側壁の光のスリットであるが、縦のスリットを、横に渡した小さなさんがちまちまと区切っている。 写真を見た時には「これは無い方がすっきりするのに‥」と思っていた。 しかし実物を見ると、この「ちまちま」によってスケールダウンして堂内が親しみやすくなっている気がした。 力学的に必要だったのかも知れないが、デザイン的にもちゃんと意図を持っている。 |
 |  | |
  | ||
 |  |
| 内壁のスクラッチ、スリットを区切る細かいさん、そしてスリットからの光、 これらは全て聖堂内部をホワ〜っと包みこむ働きをしている。 そもそもそんなに大きくないお堂だし、とてもインティミットな空間だ。 ディテールや光が集会の雰囲気密度とでも呼ぶべきものを上げている。 これを見る前日に、丹下の東京カテドラル聖マリア大聖堂を見ていたのだが、 同じモダニストでもこうも違うか、という感じだ。 丹下のマリア聖堂は上へ伸びる「ために」ある聖堂で、このアンセルモは集会の「ために」ある。 丹下のは巨大で記念碑性が強く、長谷川堯の言うところの「神殿建築」であるが、 このアンセルモはそうではない。 |
| レーモンドは日本の伝統建築にモダニズムを見出して感激した人であるが、 構造体を率直に見せて「何も引かない、足さない」を是としていた。 この教会堂も、ディテールの形態を見ると気配りはしてるんだけど、 何というか、スタンドプレー的な形態の操作ではない。 レーモンドはしぶくて、場合によってはある種の地味さとか、とらえどころのなさが感じられる(気がする)。 でもよく見ていると、簡素さを尊ぶレーモンドの意図が分かるような気がしてくる事がある。 そういう時というのは、必ずディテールから何か印象を得ているようだ。 |
| 地味というので思い出したが、村野藤吾も地味な(あるいはすっきりしない)「モダニスト」だ。 これも、こちら側から見方を変えなければならない。 レーモンドや村野藤吾は、いかにも分かりやすいおいしい味にだけに慣らされてしまった私のような人間に、 違う見方を突きつけている。 長谷川堯のいうところの「獄舎建築」とは、レーモンドや村野の建築が醸す手触りと関係ありそうだ。 スタンドプレー的でない建築の味わいである。 |
 |  | |
  | ||
 |  |
| 最後に配置計画について一言。 この教会の敷地は道路に面して細長く、機能としては礼拝・集会と牧師の住居が必要とされた。 聖堂をなるべく独立的に扱い、しかも外からよく見えるようにしたければ、 現行のように敷地の左右両端に聖堂と牧師館(1F集会室/2F牧師住居)を配置し、 真ん中を抜くのが正解だろう (正確に言うと中央部分は奥からホール、中庭、アーケード、駐車場である)。 レーモンドが実際どう考えたのかはわからないが、外から良く見える聖堂であるというのは、 開放された感じがしてよいと思う。 逆にクローズに作る事も充分考えられた筈だが、 それでは開放性を重んじるカトリックの聖堂に似合わない。 |
|