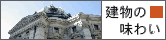設計:シーラカンス
| * | 屋根がひらひらと多様で内部空間も多様 |
| * | スロープや階段が多く、交差する動線 |
| ピースおおさか(旧名「大阪国際平和センター」)は、 1989年にコンペがあり、原広司、長谷川逸子等を審査員として迎え、 シーラカンスが一等をとって実施設計したものである。 コンペの時シーラカンスはできて4年目であり、 この頃は全員一致という厳しい共同プロセスで作ったそうだ。 |
| 敷地の南側は大通りに面して高速道路が走り、北側は大阪城公園に面した閑静な環境で対照的である。 建物は北側にある中庭を囲む様に幾つかの棟に分かれて配置され、 入り組んだ棟構成が中庭をはさんで、色々なレベルを生じさせている。 屋根が随所でひらひらとして変化が付けてある。 内部には階段と、バリアフリーの為のスロープがやたら目に付く。 要するに全体が空間的なバリエーションの発生装置となっていて、 内部はスロープや階段を通じて色々な通り抜けができるようなイメージが醸し出されている。 この様々な場や屋根は、様々な思想・民族の共存を表しているそうだ。 これを見に行った日に、 こどもの街 (キッズプラザ大阪、フンデルトワッサー原案)も見たのだが、 入り組んでバリエーションの中を歩かせるのは、こどもの街の大人版とさえ思えた。 |
| しかしそれにしては、何となく空間体験的にこなれない感じが残った。 閉館ぎりぎりに急いで見て回ったのでじっくりとは見てないのだが、 せっかく屋根が多彩でも、その下の空間がそれに見合う面白さを持っているとは限らない。 バリエーションによる表現、という建物全体の趣旨は感じられるにしても、 味わい深い空間になり切っていないところが多いのではないか。 また通り抜けという事で言えば、運用上の都合で一部の階段が通行禁止になっていた。 |
 |  | |
  | ||
 |  |
| のちの1999年に小嶋一浩等が作った ビッグハート出雲 は、空間構成的にシンプルだが、 それでも空間に濃密な意味が与えられていたように思う。 約10年の間に表現方法も変わったし、空間演出力が洗練されたのではないか。 勿論ピースおおさかはこれで空間的なバリエーションを広げてゆく好例であり、 「こういう作例もある」と見て参考にするにはたいへん重要だと思う。 |
|