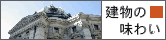設計:第四師団経理部
| * | 中世様式的な意匠で軍組織の威厳を表した。しかし今見ると瞑想的ですらある |
| この建物は1931年(昭和6年)に第四師団司令部として軍により建てられた。 時代的に言うと、昭和5年に有名な東京帝室博物館のコンペがあり、 公共建築には帝冠様式が吹き荒れていた。 場所が大阪城から至近距離だし、ここも当然「和風」にしないか、という要請があったと思われる。 しかし設計者は敢えて中世様式を取り入れた。 昭和初期にはモダニズム建築も作られ始めているが、 歴史様式の建物としてはクラシシズム系(古代ローマ的)が多く作られたという。 その前の大正時代には、表現主義やゼツェッションが風靡した一方、 歴史様式の建物としては中世様式(ロマネスク、ゴシック)が多かったそうだ。 その意味では、昭和6年に中世様式というのは様式建築としても少数派であろう。 外壁上部のロンバルディアバンド、そして 中央塔に付いた円筒形も「ロマネスク・リバイバル」の意匠に属する。 |
 |  | |
  | ||
 |  |
| さて見た印象であるが、何とも古い煉瓦の色、壁の色、ひびの跡。 その「古び」と共に建物の外形が一種の瞑想をもたらしていた。 建物というのは常に歴史を体現しているものだが、 この建物からは「歴史」が見えてきた、という感じはしなかった(私にとっては)。 この建物から見えてきたのは、 まずもって「軍」という国家機能を表象する為の、意匠による装置としての建築である。 当時は軍の施設だったわけだが、軍の公務を何とも上手に表している。 日本におけるビルディングタイプごとの西欧デザインの使い分けが、大変わかりやすく伝わってくる。 陰と陽で言えばこれは陰の建築に思える。 軍の公務を体現するといっても華々しい感じではなく、何というかなぁ、 日々の生活に隷属された私、みたいな実存感覚につながる気がする。 だから長谷川堯流にいえば「獄舎建築」に属するだろうし、瞑想的にもなる。 |
 |  | |
  | ||
 |  |
| 見た時にちょうど夕日が当たっていて、ファサード中央が金色に輝いた。 夕陽はこの建物にふさわしく思える。 今はもう博物館として使われていないのだが、今後果たして保存されるのか否か‥。 「この建物をなぜ残したいか」ともし問われたら、その理由として、私が最初に思いついた言葉は 「古いものへのいたわり」であった。 いたわりさえ失ったような世界(社会)には生きたくないものだ。 あなたもそう思うでしょう?。 |
|