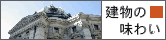設計:岡田信一郎
| * | 当時の新鋭だった岡田によるフリークラシックの構成 |
| この公会堂は非常に有名な建物だから、ご存じの方も多いだろう。 正面から見ると、大アーチ窓が何と言っても印象的である。 その下の4本のオーダーと共に、 「どうだ!見てちょうだい」と言わんばかりの偉容と言うべきか、 建てた人の顕示欲というか、そんなものが私には感じられる。 その両側に塔が立っていて、更に筐体がハミ出ている。 こんなスタイルは、特定のリバイバル様式にあてはまらない。 そう、設計者である岡田の作った「フリースタイル」なのだ。 こういうのをフリークラシックという。 |
| そもそも西欧でも20世紀に入って、特定のリバイバル様式でない様式建築が現れ始める。 当時のエコール・デ・ボザール卒業生の作風は、 様式の建築言語を組み合わせる自由さにあったという。 例えばNYにあるキャス・ギルバートの 旧合衆国税関 (1907)はバロック復興的であるが、 様式言語と彫刻表現を自由に駆使している。 |
| しかしそれにしても中之島中央公会堂は独創的だ。 コンペ案の図面を見たことがあるが、岡田のパースは幻想的であった。 日本でこんな幻想的な様式的建築が作られたのは、 明治ではない大正という時代が大きく関係していただろう。 明治時代には、このように幻想的なものに沈潜する精神的余裕が生まれなかったであろう。 とはいえ、実物はこの岡田案通りに作られたわけではない。 例えば左右の塔の窓は、審査員だった辰野金吾などが幾何学的に単純化してしまっている。 岡田はこの処置にかなり不満だったらしい。スケール感が多少粗くなってしまっている。 |
 |  | |
  | ||
 |  |
| こんな建物をニューヨークで見つけたら、どんな気分がするか想像してしまった。 まず感じるのは幻想的だということである。 側面の窓とピラスターの装飾などはまさに幻想を増殖する為にある(ように感じられる)。 現代建築では決して表現し得ない、どこの時代から生まれてきたのか分からないような建物だ。 ふと私は、この建物から出てくる幻想性は、建物が壊されても他の世界に生き続けるような、 そんな「幻想」に囚われてしまった。 特定の時代を表現しなくて宙に浮いているから、逆に時代や時間を超越してしまっているのだ。 |
| 私はまだまだ変なことを考えた。 この公会堂は岩本栄之助という実業家の巨額の寄付でできたのだが、 彼は寄付の後に株式相場で手痛い失敗を喫し、自ら命を絶っている。 だから彼はこの公会堂の落成式に立ち会っていない。 この建物の不思議な永遠性は、実は岩本の属する異界と関わり合った結果ではなかろうか‥。 この建物は、実際にも一度命を落としかけている。 公会堂は1971年に大阪市によって解体の方向が提示された。 その後、建築界や中之島を守る会などによる熱心な保存運動があって、 公会堂をはじめとする中之島にある多くの歴史的建築物が保存されたのだった。 |
| 最後に2004年にローマ旅行から帰ってからの印象を書いておく。 この公会堂はフリークラシックの幻想的雰囲気を多く持っていると書いたが、 ローマを見たあとでは正面左右両肩の塔のデザインが何とも中国的に見えた。 やはり何とはなしに日本的な様式建築となっている。 この建物のすぐ脇にある 大阪府立中之島図書館 もそうだ。どことはなしに日本らしい様式建築である。 |
|