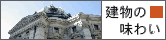設計:妻木頼黄
| * | 端正で密度の濃いディテールの様式建築。現存する妻木の代表作 |
| 旧横浜正金銀行本店は1904年(明治37年)の竣工の様式建築で、 妻木頼黄らしい多少アクのあるドームが特徴といわれる。 しかし実物は端正で、アクという感じは全然受けなかった。 ただ、ドームの丸窓や湾曲の具合が幻想性を感じさせるのは確かで、 同じ妻木の日本橋の彫刻の動物のように、 ヨーロッパの様式意匠の中でもゴシック的な(?)幻想の系譜を持ち込んでいるといえる。 辰野や曽禰、片山といった他の様式建築家はそういう意匠の幻想性を強調しないので (片山は多少使うし伊東忠太は好きそうだが)、 妻木の意匠はアクがあると言われるようになった所以であろう。 ただ本当に妻木の意匠の「アク」が知りたければ東京の日赤本社を見なければならなかっただろう。 但しそれはもうとっくに取り壊されてしまっている‥。 |
| 外装はジャイアントオーダーのピラスター(付け柱)に覆われ、 その意味ではバロック的なのだが、オーダーや全体の印象が端正なのはルネサンス的でもあろう。 私は最初この建物を夜のライトアップで見たのだが、 その時は大変幻想的な美しさを感じた。 昼間見ると端正なオーダーの意匠も、うす暗く下から照らされると雰囲気をガラっと変える。 そして夜だから細部が見えない。 外国で様式建築を見た時に、細部が凝っているとスゴい幻想的迫力があるのをご存じだろうか。 それの裏返しが起こった。よく見えないから細部に実はスゴい彫刻が施されているかの如くに見えて、 私の想像の中で、ど迫力に満ちた超幻想的な(!) フリークラシックの建物のイメージが膨らんでしまった。 鬱蒼とした光と影を持つ時代を超えた建物、外国で見ているようなデジャブ‥。 |
 |  | |
  | ||
 |  |
| 翌朝、日の光のもとで見た建物は、昨夜思ったより平板だった。 そりゃそうだ、ここは日本だもの。 日本人が設計し日本人の手で作る様式建築では、彫刻の迫力には滅多にお目にかかれない。 様式建築の彫刻のド迫力に出合いたかったら外国へ行くしかない( 明治生命館 が僅かにそういう素質を持っているが)。 つまり昨夜は暗いからスゲェ〜美人に見えたのだ。 まぁ確かに、非常にこまかい細部は思ったより簡素であったけれども、 ディテールの密なデザインは構成がとてもしっかりしている感じだった。 石の目地がデザインによく生かされているといえる。 |
| 正面入口から内部に入るとホールに天窓があるが、 当初はこの踊り場は吹き抜けだったのではないのかと思う。 設計当初の内部の空間性(空間の良さ)は、今となってはとても検証できない。 とにかくこの建物は神奈川県立歴史博物館になった時点でかなり変わった筈だ。 博物館への用途変更でこの建物は見事に保存されたのだが、 そのとき外壁保存がなされドームは復元された。 裏側は徹底的に変えられて、新しい正面入口が裏に付いた。 でも当初の正面入口は今でも入れるようになっている。 |
| 最後に妻木について述べておくと、 彼は政府の営繕のポストに長らくついていた。 表舞台の辰野に対し、裏方として隠然とした力を発揮したと言われる。 東大・コンドル路線の辰野・片山・曽根等のイギリス仕込みに対抗し、 ドイツに学んで違う系統の様式意匠を持込んだ。 国会議事堂の建設計画に当たっては、辰野と大々的なつばぜりあいを演じた事でも知られる。 またこの建物は、修業時代の遠藤於菟が現場監督を務めていた。 |
|