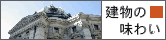設計:日建設計・三菱地所
| * | 巨大吹き抜け空間を持つ商業施設。そのような巨大吹き抜けは1990年代に多く作られた |
| クイーンズスクエア横浜は、みなとみらいの高層ビルの低層部にあって、港を見下ろせる場所にある。 中は、高層ビルを貫通する、3層以上の高さのある広大な吹き抜け通路となっている。 その中心部に、これまた有名になった巨大吹き抜け空間がある。 これらはでかい。ちょっとスケールオーバーに見える。 たとえお客が充満していても、尚かつ広大すぎて空虚を感じさせてしまうようなスケールなので、 お客が閑散としていると本当に淋しい。 そして私達が行った時にはお客が少なかった。 |
| くだんの吹き抜けは、一方がみなとみらいを見渡す広大なガラス面になっている。 外国のリゾートホテルによくある吹き抜け空間を更にバカでかくしたような感じだ。 ここは大きなエスカレーターが有名で、吹き抜け空間をそれに乗って下から上がってゆく。 その移動が、空間全体にも動きをもたらす筈だった。 「筈だった」というのは、そのエスカレーターが今は停止しているからだ。 吹き抜けに面したフロアの一部に椅子があって人がたむろしているが、動きはない。 でかい空間全体が静止しているかの如くで、商業的には死んだような空間なのだ。 ここは現在、不況で苦境に立たされている。 この空間の淀みは、まさに経営不振を見える形で表していた。 |
 |  | |
  | ||
 |  |
| しかし、元々どういう意図でこの空間が作られたかは、充分に想像できた。 各階の色々な形をしたデッキが重なり合い、その至る所に色々な方向に人の流れができる。 各デッキの多様な人の流れは、 例えば巨大なビジネスプロジェクトにおいて人々がそれぞれの仕事にいそしんでいる状態のように、 人々に連綿に似たものを感じさせるのだ。 吹き抜けの周囲には平面が四角い黒い障害部分がわざと作ってあって、 逆にデッキの「各所性」とでもいうべきものを引き立てている。 デッキにはあらゆるバリエーションが発生していて、 様々な方向、場所、空間的ニュアンスを変えて人々が動き回る。 「同じ屋根の下」という連帯感が、言葉上の比喩ではなく身体的なものとして体験される。 それがかりそめの一体感というイリュージョンを生み出すのだ。 |
| このような吹き抜け空間が商業的に魅力を持ったのは、19世紀パリのボン・マルシェ以降のことである。 しかし、ジャーディ・パートナーシップ原案のキャナルシティ博多(1996)が日本に登場して以来、 商業的吹き抜け空間は、かりそめの見る←→見られるの関係を作り出す装置として新たな意義を持ち始めた。 商業空間の変遷を追っている建築史学者中川理(なかがわおさむ)氏によれば、 それまで樹木構造の会社組織で働いていたサラリーマンのメンタリティに沿って、 東京タワーのような俯瞰装置が人気を集めていたのに対し、 1990年代の人々はネットワーク化し始めた。 |
| ネットワークの中のノードやリーフでしかない自分の孤独を癒す方法は、 それまでのようにヒエラルキーの中で自己確認をする (=東京タワーのような高い場所から俯瞰をする)事ではなく、 キャナルシティ博多やクイーンズスクエア横浜の吹き抜けのような、 囲われた空間の中で共に存在する事の、共同的自己確認であったというのだ。 東京国際フォーラム(1996)だって、 JR京都駅(1997)だって、巨大な見る←→見られるの関係性の内部空間を作っている。 囲われた巨大空間というのは確かに1990年のはやりだったのであり、 それを望むメンタリティの存在はたとえ仮説であるとしても、事態解明の有力な手がかりとなる。 |
 |  | |
  | ||
 |  |
| 一方、1994年の 新横浜ラーメン博物館 以来、フードテーマパークという全く別種の商業空間も登場している。 しかし、これもやはり何らかのテーマや物語性(身近な歴史性)の中に人々と共に居るわけで、 共同性と共同的自己確認が問題となっていると考える事ができる。 ヴィーナスフォート(1999)も、その内装が人々を同じ歴史性・物語性に居合わせさせるのだから、 同じような空間装置と見なせる。 つまり、これらは一見別々のものに見えても、 巨大吹き抜け空間とある意味で同じ目的を持っているといえるのだ。 |
| 但し今は不況なので、 大がかりな吹き抜け空間よりこじんまりしたテーマパークの方が合っていると言えるだろう。 実際、クイーンズスクエア横浜は上述のとおり閑散としていて可哀想なくらいであった。 2000年になってからというもの、巨大吹き抜け空間は作られただろうか。 どうもこれにも、はやりすたりがあるようだ。 しかしもし中川理氏の言う事が正しいとすれば、 ネットワーク社会の(あるいは故郷喪失した)人々の孤独を癒す為の空間的装置が、 これからもますます作られ続ける筈である。 ただどういう形態になるかは分からない。 テーマパークもすたれるかもしれない。 その時どんな空間が(主に商業空間が)私達の前に現れるのであろうか。 |
| 補注:巨大吹き抜け空間は囲われた感じを我々に与えるが、 これについての私なりの見解を、ここで発表しておく。 これはJ・デリダが言うような「自分の声を聞く」装置に他ならない。 ここで「声」とは近代的意識・主体の同一性を保証する作用を指す隠喩である。 「声」は発すると同時に聞く事ができる。 近代的主体は、経験的自我のレベルで起こったことを、声を介してそのまま耳にし、 「私は聞いている」という超越論的自我のレベルで同時的に自己確認(自己中心化)する。 つまりオブジェクトレヴェルの自我とメタレヴェルの自我とに単一の主体がたえず二重化され、 その二重化の運動によって同一性が保たれているのだ。 |
| 「私は歩いている」というのがメタレヴェルの私だとすると、 囲われた感じの中にいる私とは「私はこの人々の中に居る私である」という、 一段メタレヴェルの認識である。 しかも、自分の声が否応なしに自分の耳に聞こえるのと同様に、 歩いているというだけで「囲われている」感じ=メタレヴェルの認識が付与して付いてくるのだ。 これは近代的自我の自己確認を強化するものに他ならない。 オーギュスタン・ベルクは、 意識的・自覚的にある景色の一部となる事を「実景」と呼んだ。 ベルクは実景こそが近代を超克する新しい意識の現れだと言ったのだが、 ここでの私の見方に従えば、 これは近代的自我の近代的自我たるゆえんをますます強める方向に向かうものだといえる。 |
| 一方、デリダが主張するように現前性の形而上学を越えて、 そうでない存在認識・時間認識に至ろうと思えば、現前性の思考をしっかり見定める必要がある。 「囲われている」感じ=メタレヴェルの認識というのは現前そのものであるから、 それを自我・意識のよりどころとする事は、デリダが指し示す方向とまさに反対である。 A・ベルクの主張は「自分の声を聞く」装置の強化に他ならない。 それが商業空間において顕著に現れるのは、 商業空間がまさに平均的大衆の無意識的な自己確認欲求にそぐうからである。 それは平均的大衆の自我・意識の同一性がおびやかされていて、 何とか保証してもらいたいと思っている事の顕れである。 もしも人々が現前性を越えて行く「べきである」と仮定するならば、 商業的巨大吹き抜け空間というのは反動的な意味合いを帯びた自己確認装置なのである。 |
| ベルクの「実景」は、このようにして必然的にキッチュな世界に貼り付く(のではないか)。 一方、宮台真司がいう「終わりなき<日常>」の世界は、彼も言うように デリダ的な郵便ネットワーク的世界認識・時間認識とかなり近しい関係にある。 その一方で、ベルクの予言に沿ったキッチュ=現前の世界がある。 これらの関係はこれからどうなるのだろうか。 何が新しい時代の夜明けを用意するのだろうか。 |
|