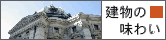設計:前川國男
| * | 前川のテクニカルアプローチの成果が出た機能主義的な公共施設。前川の建築にただよう空間性 |
| 前川国男が作る空間には、単に「合理的に配置したまでだ」という以上の空間性が宿っている。 平面や配置計画は師のコルビュジェより単純明快な感じだが、 無駄をそぎ落とした機能的空間の潔さみたいなものを、 うまく表現するツボを心得ているように思う。 例えば柱・梁の見せ方とか材質感、外壁や開口部の仕様、 ごくさりげなく配置したような階段や回り廊下とか、 そういうものが持つ空間的効果を前川はよく知っていた。 彼は戦後、工業技術時代にふさわしい建築構法の開発・普及に努めた人だったけど、 同時に、当時先端の建材・構法からどんな建築表現が生み出せるか人一倍考えた人だと思う。 そういう前川が作った空間の例として、例えば京都会館(60)が挙げられる。 東京文化会館(61)は、前川の作る空間の特別豪華版って感じだ。 そしてこの神奈川県立音楽堂・図書館(54)は、 逆にどちらかというと簡素版という感じだ。 何しろ時代が1950年代半ばだし、自治体もお金を持っていなかったろう。 かなり切りつめた予算の中で作られたのではないか。 |
 |  | |
  | ||
 |  |
| この音楽堂はロイヤル・フェスティバル・ホールを参考にしたと言われる。 って、あのロンドンの これのことですよね。 あれなら私も行ったけど、そんなに覚えていない。 立派で大きいフェスティバル・ホールから何を学んだんだろう?、 客席がせり上がる真下をホワイエにしたとか、そういう構成の事だろうか。 それなら京都会館も同じである。 とにかく県立音楽堂はこじんまりしていて、音響的にもすぐれ、暖かみのあるホールとして定評がある。 一方、図書館は中央を書庫とし、 耐震壁を書庫まわりなどに配置することで外壁部分を軽量化して大きな窓を取り、 閲覧室を窓に面した明るいものとした (但しプライバシーの観点から外壁に一部CBが回してある)。 |
| これらの建物は、90年代に保存問題で脚光を浴びた。 この音楽堂の取り壊しが決定されかかったとき、 「解体派は、機能主義の建物は機能が適合しなくなったら取り替えられるのが運命だと言っている」 と、まことしやかに言われたものであった。 私はこのホールで実際に音楽を聴いたことはないが、外から見た限りでは、山口半六の 奏楽堂 を思い出してしまった。 両者はまるで違うが、共通してこぢんまりしていて、音楽の場として人々に愛された。 奏楽堂は、とりたてて空間の特徴がどうのこうのというような目立つ特徴はなくて、 淡々と必要な部屋機能をつないでいるだけだったが、 それでも2Fのホールは小規模で家族的ともいえる暖かみを感じさせた。 各部屋々々は節度や品位を感じさせるものであった。 |
| さぞかし多くの人々のドラマがそこで起こったことであろう。 各部屋々々の節度や品位、暖かみといった空間的特質が、そこで生活する人の背景として常にあった。 そして人々はいつまでも奏楽堂の事を忘れなかった。 神奈川県立音楽堂も機能中心に作られているにもかかわらず、人々の記憶に残った。 これらの建物は非常に異なるにもかかわらず、 愛される素質とでも言うべきものを持っていた、という点で共通している。 どちらの建物も、人々の活動の<背景>として気持ちの中に建物が残っていくような、 そういう空間の質を持っていたのだと思う。 それは、多くの建築家が大上段に構えて「空間性」と述べるものとは違って、 きわめて淡々としたものであろう。 とても見過ごされやすい空間の質だと思う。 しかし、「機能が変わったから取り壊す」なんて簡単に言えない重要な質だ。 そういう空間の質(空間性)をより解明するような研究が、 もっと建築関係者によってなされて良い筈だ。 |
 |  | |
  | ||
 |  |
| ただ最後に蛇足をひとつ。音楽堂を出てふっと目を「みなとみらい」に移すと、 そこにはランドマークタワーなど近未来的な建物が燦然と並んでいる。 目をもう一度戻すと、音楽堂がいかに「ボロい」か分かる。ぶっ壊れそうだし。 隣の青少年センターも負けずにボロい。 ホントに建物って色々あるなぁ。 音楽堂・図書館は、市民の厚い好意に守られてこれからも存続しつづけるだろう。 |
|