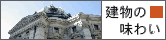設計:伊藤豊雄
| * | 「何の為」と活動をちまちま分けない、もっとボーダーレスな活動の起こる<場>を建築化しようとした |
| この建物は「どこが正面」という感じがあまりしないのだけれど、 とにかく北側に道路があって、そこから文化プレイスに向けたアプローチが設定されている。 中にはいるとそこは劇場(ホール)のホワイエになっていて、出入口が幾つかある。 しかし、同時にそこは建物全体のロビーであり、喫茶ラウンジに通じている。 ラウンジや劇場、その他の活動が、互いに区分されずにごっちゃに混ざるような、 そういう融通無碍な空間がそこにできている。 天井は高く、天井近くで全ての空間が繋がっている感じがする。 細い丸柱と天井、大きなガラス面の作り出す透明なリズム感が全体を覆い、 部分よりも、それを包む全体の中にいる感じの方が強くなる。 サインやインテリアデザインも、垢抜けた空間性に寄与している。 とにかく「ここは何する場所ですよ」という規定が感じられず、 「みんなが集まって色々な事をしている」 全体感(あるいは連帯感)の方が先にある、そういう空間だと私は解釈した。 そう感じられるように、 空間の「無規定性」みたいなものが内部のディテールや素材によって演出されている。 |
 |  | |
  | ||
 |  |
| まぁそういう事だと思うんだけれど、実際には人が誰も居ない寂しさの方が強く感じられた。 そこには、人口も少ないのにこんな公共施設を見栄で(?)作った自治体の 「つもり」と「誤算」がそのまま出ている気がした。 劇場も公演予定が貼り出されていなかったから、ロクに使われていないようだ。 設計者である伊東の意図と運営側は時に対立した。 伊東が主張するような「ボーダレス」にされると管理が面倒だから、 施設を明確に分けてくれと注文が付いたという。 責任範囲を分けられないし。 図書館が他とガラス壁で仕切られているのは、その注文のせいらしい。 その区分に合わせて、図書館だけは建物の構成的にもちゃんと別れていて、 形と区分がきれいに合っている。 設計者としてはそこを出来るだけ繋ぎたかったし、境目を溶かしたかったのだが、 図書館は館長も違うし管理が違うから別にしてくれと、言われ続けたらしい。 |
| そもそもコンペを取ったときの模型を見ると、円形で遊園地みたいな建物に見える。 実施された建物ではそれがすっかり変わって、ご存じの柔らかいフォルムとなった。 当初、歌舞伎をやる大上段に構えた施設だったものが、 地域住民の為の地域に溶け込んだ施設へと変更された事が、施設のフォルムにも出ている。 ぐるっと建物の周囲を回ると、曲線を使った建物の内部空間の魅力が想像されてくる。 会議室や図書館には丸い円周を四角く切った庭があり、 町家の坪庭のようなスポット的な効果を得ている。 いずれにせよ、伊東豊雄はきわだった「裏」を作らないようにしたいと考えたそうだ。 この敷地には強い軸も正面もないし、 いかにもそれと分かる「裏」ができるとクサくて暗い建築になる(気がする)。 また、建物の北端(入口に向かって歩いてゆくところ)では、 お客さんと反対側の楽屋のスタッフが互いに見通せるようになっている。 これが何故か「うまい」と思った。 劇・公演をやる側の人と、見る側の人の視線が出会い浸透する、 つまりこれも一種の「透明性」なのだ。 |
 |  | |
  | ||
 |  |
| ただ、実物を見る前から一つ気になっていた事があった。 それは劇場(だんだんホール)の両脇が空いている事だ。 東側はエントランス通路で、通路の一部は天井を低くしてある。 その天井の上は無為の空間に思える (設計者にしてみればもちろん意図的に作った空間なのだが)。 西側は箱段が積まれているだけで、その外側部分はだんだんテラスと呼ばれている。 だんだんテラスは野外ステージなんだけど、 この自治体では使われないのが目に見えているのではないか。 そこまで考えると、積極的な空間の意味あいが演出され切っていないように感じてしまう。 伊東豊雄くらい巨匠になると、無駄なあそび空間があっても許されるのか(?!)。 ただそれでも、ホール両脇を開けてそこから自然光が入るというのは、 外の気配が壁を突いて入ってくるわけで、筒抜けている、つまり一種の透明性である。 伊東はホール両側に無為の空間を作ってでも、 この透明性を実現させたかったのではないだろうか。 |
|